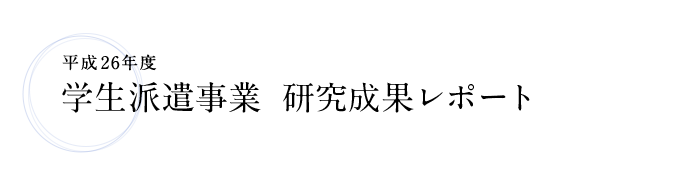宇佐美 智之(国際日本研究専攻)
1.事業実施の目的
国際会議Conference on Cultural Heritage and New Technologiesにおいて研究発表をおこなうこと、また、学位申請論文の執筆に関係する資料の観察・収集をおこなうこと
2.実施場所
ウィーン,オーストリア
3.実施期日
平成26年 11月1日(土)から 11月8日(土)
4.成果報告
事業の概要
オーストリアのウィーン市庁舎で開催された国際会議において、研究発表をおこなった。
当会議は、都市考古学(Urban Archaeology)という分野を基礎としながら、最新の技術や方法論をもちいた調査・研究についての活発な議論がかわされる場である。毎年ことなるテーマが与えられ、それにしたがってセッションやワークショップなどがすすめられる。2012年大会の「発掘」(Excavation)、2013年大会の「ドキュメンテーション」(Archaeological Documentation)というテーマの流れを引きついで、今回の大会では、「考古学的データの処理と分析」(Processing and Analyzing the Data)というテーマが選択された。
考古学の研究を支えるのは発掘をはじめとする各種の現地調査の作業であるが、それらをおこなえばおこなうほど、通常得られる資料数は増加し、それにともなって全体の把握は難しいものとなる。長期の調査をつうじて膨大な量の資料を蓄積できた場合においても、その一方では資料の種類は多くなり、その質の面ではばらつきが大きくなる、という傾向が生じるために、それらの運用自体が困難になることも少なくない。こうした問題は、近年、ますます重要なものとなってきている。各々の課題の解決にむけてそれらの資料を十分に役立ててゆくうえでは、資料の整理・分類、データの作成(情報の抽出)、データの分析、といった種々の作業への取り組み方が重要となるであろう。今回のテーマはその方法・視点とプロセスに焦点をあてたものであり、従来の研究の到達点と問題点、また、最新の技術や方法論などとの関連のなかで、それらを具体的に捉えなおそうというねらいがあった。
ところで、先に「都市考古学」という分野にもふれたが、当会議において想定される「都市考古学」の射程は、先史時代から近現代にまでおよぶ。「都市」そのものに関する研究にかぎらず、都市化(Urbanization)に関連する研究などをも幅広くふくむようにして、議論がおこなわれるのである。時代・地域によっては、たとえば先史時代に「都市」が存在したか否か(「都市」という用語を使用してよいか否か:その定義や認定をどうするのか)といった点が問題となることもあろうが、ここでいう「都市考古学」がそのような問題につよく規定されるような性質のものではないこと(いわゆる「都市の考古学」ではないこと)を確認しておきたい。
当会議は3日間(本年度11月3日~5日)にわたって催され、そのなかで約10のセッションが開かれた。会場が2つにわけられたため、そのすべてを聴講することはできなかったが、報告者が参加したもののうち、とりわけComplex Archaeology meets Complex Technology、およびAnalyzing the Deadのセッションは参考になるものであった。特に前者は本大会のメインとなるようなセッションであり、考古学的データの処理・分析にかかわる理論的問題を整理しつつ、その検討にもとづく事例研究の成果が示された。報告者が現在関心をもつ先史時代の集落構造(Settlement Pattern)に関する研究報告もいくつかあり、それらの方法・視点には多くを学ぶことができた。ただし、このなかでは報告者の知識不足などに起因するような問題もあった。本大会では、ヨーロッパの各地・各時期が事例研究の対象となることが多かったが、それらのコンテクストの知識、またはヨーロッパ史に関する理解が不足していたために、もっとも重要となる研究成果(結論)の意味・意義を十分につかみきれなかったものもあった。その後のディスカッションなどをつうじてある程度把握できたものもあったとはいえ、事前の準備の重要性をあらためて痛感するとともに、他方では私自身のプレゼンテーションにおいても同様の事態が起こりうるということを実感した。当然のことながら、主張・強調したいところで単に声を張りあげればよいというわけではなく、それを効果的に示すためには、プレゼンテーションの全体が十分に整理・デザインされていなくてはならない。決して容易なことではないが、今後はそのような取り組みをつうじてより有意義な議論を引きだせるよう、努めたい。
本事業では、当会議における活動のほかにも、主に自然史博物館(Natural History Museum)とローマ(時代)博物館(Roman Museum)において、学位申請論文の執筆に関係する資料の観察・収集の作業も実施した(実施日:国際会議終了後の11月6日)。限られた時間ではあったが、実際の考古資料(遺物・遺構)を見ることができたのは貴重な経験であった。また、可能な限り、写真および遺物・遺構の属性情報を集めて、データベース化n作業をすすめた。上に述べた国際会議での経験とあわせて、今後の活動/学位申請論文のなかで役立ててゆきたい。
学会発表について
本年度、報告者は、北部九州地方の弥生時代の甕棺(墓地)資料の分析に力を注いできた。甕棺をもちいた埋葬習俗、ならびに墓地を手がかりとして、当該地域・時期の社会の特徴とその変容のプロセスについて考えることが目的である。本発表の内容もこれにもとづく。
具体的には、1) 広域的なスケール(北部九州地方全体)の甕棺墓分布の変化、2) 局所的なスケール(主に佐賀平野および吉野ヶ里遺跡内)の甕棺墓の形成プロセス、以上の2つに重点をおき、定量的手法(およびGIS)をもちいながら分析・検討をおこなうことにした。1) の検討に際しては、まず、既存の調査報告書等から構築されたデータベースをもとに時期別・型式別の分布図を作成し、そのうえで空間補間技術(Inverse Distance Weighted:逆距離加重法)などを利用したデータ処理・分析(モデリング)の作業をおこなった。また、2) の検討に際しては、佐賀平野(東部)と吉野ヶ里遺跡に分析の的をしぼり、各調査報告書を利用して、発掘調査区域(トレンチ)単位での甕棺の型式別空間密度解析などの作業を実施した。以上のようなとりくみをつうじて、ミクロ・マクロに甕棺墓の動態を考察し、最終的には埋葬習俗や墓地の広がりの様相から見た当該地域の弥生時代社会の特徴について論じた。あわせて、その結果の一部を、日本列島や東アジアの都市化のプロセスと関連づけて理解することもこころみた(口頭での言及のみ)。
以上の内容のなかでも特に質問や指摘を受けたのは、①上記1) の検討で扱った分析手法(上に述べた空間補間技術の適用・応用)、②甕棺の型式分類の仕方、③データベースの作成と利用の方法、などに関することである。これらは分析結果に直接関係する重要な問題であったので、より分かりやすく具体的な説明を加えるべきであったと反省した。一方、上記2) の検討に関しては、分析の手順や結果・解釈の面で一定の評価を得ることもできた。よかった点、改善すべき点を整理し、今後の研究につなげたい。
本事業の実施によって得られた成果
a) 上にも述べたように、一定の評価を得られた箇所と、問題を指摘された(または十分な理解を得られなかった)箇所がはっきりしたことは、大きな収穫であったといえる。また、他国の研究者との意見交換をするなかで、次に学ぶべきことがより鮮明になったことも非常に重要であった。
b) 諸博物館において実際の考古資料(遺物・遺構)を見ることができ、また一部のものの写真・属性情報等を集めることができた。展示資料の多くはヨーロッパのものであり、報告者が研究の対象としている日本列島とは遠く離れた地域の資料である。とはいえ、それらを相互に参照する視点は重要なものであり、直接的にも間接的にも、博士論文のなかで役立てることが可能と考える。
c) 国際会議での活動をつうじて、自らのプレゼンテーションをあらためて見なおすことにつながった。今大会の特に印象深かった場面として、ある発表者に対し、「結局何を明らかにしたのか」という厳しい口調のコメントがむけられたことがあった。その発表が内容的に乏しかったわけでも、発表の態度・姿勢が問題であったわけでもなく、さらに当然結論も示されていた。偶然にも、私自身の研究と関連する対象・内容であったので、私には発表者の結論の意味・意義を(私なりに)把握・推測できた。が、おそらくは、結論の前提となる理解または背景的な知識などに大きなギャップが生じていたことで、さらには伝え方が適切ではなかったことで、このような事態が起こったのであろうと推察される。どのような会議においても同様のことは生じうるとはいえ、国際会議のような場、それも当会議のように多様な分野の研究者が集まる場では、伝え方次第によってそのような問題・誤解をより招きやすいのではないか。こうなってしまうと、議論がなかなか進展しなくなることもある。この場面に遭遇した後には、いくつかのセッションを聴講してゆくなかで、プレゼンテーションのあり方の問題についても考えるよう努め、会議最終日には、それに関してほかの数名の参加者の意見を聞くこともできた。研究内容とは関連しないが、これも貴重な経験となった。
本事業について
上に示してきたとおり、この事業をつうじて得られたこと、学んだことは多くある。なによりも、それらのことごとを次の活動(博士論文)のなかで活かすことで、本事業の重要性を証明できるよう努めたい。